採用課題とは?よくある課題一覧と解決策を解説
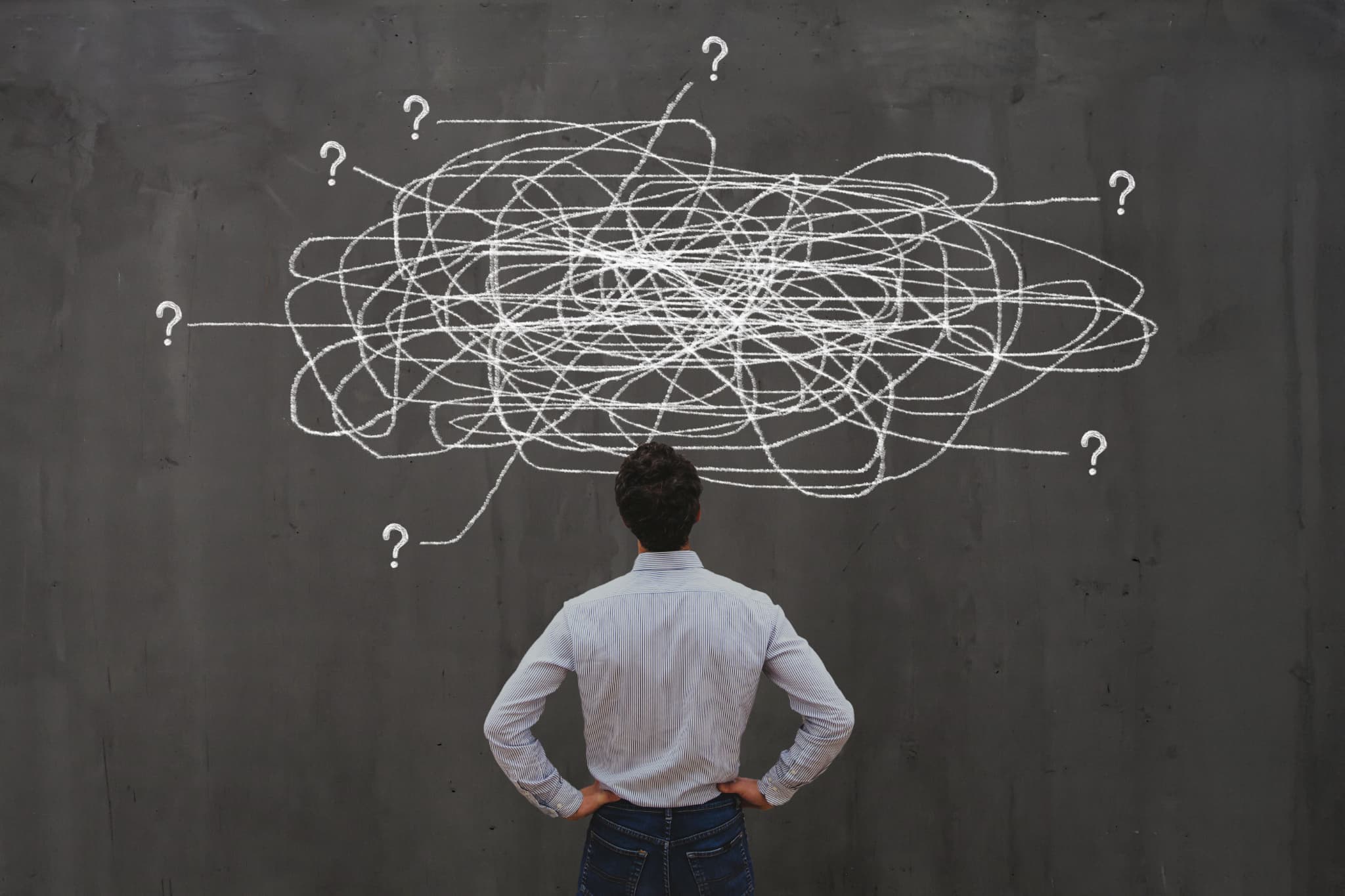
目次
積極的に採用活動をしても上手くいかず、採用課題を把握できていない企業は少なくありません。採用課題がわからないまま放置してしまうと、採用活動に支障をきたすため、課題を特定して対策を講じることが重要です。
当記事では、採用課題を明確にする重要性や企業が直面しやすい課題一覧、さらに実践的な解決策について解説します。
採用の質を向上させたい企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
採用課題とは

採用課題とは、企業が人材を採用する際に直面するさまざまな問題や障害を指します。これらの課題は、企業の成長や競争力に大きな影響を与えるため、適切な対策を講じることが求められます。
採用活動が上手くいかない理由を理解することで、企業はより効果的な採用戦略を構築することが可能になるでしょう。
採用課題を把握することの重要性
採用課題を把握することで、企業は自社の強みや弱みを理解し、戦略的な採用活動を展開することが可能になります。採用課題を改善できれば無駄なリソースを削減し、効率的な採用プロセスを構築することもできるでしょう。
例えば、応募者が集まらない場合や求める人材からの応募が少ない場合、その原因を特定することで、課題に対してピンポイントな対策を講じることができます。これにより、採用活動の質を向上させ、企業の競争力を高めることができるのです。
自社の採用課題を把握する方法
自社の採用課題を把握するためには、まず現状の採用プロセスを詳細に分析することが重要です。具体的には応募者数や選考通過率、内定承諾率などのデータを収集し、数値的な視点から問題点を洗い出します。
客観的な数値から分析を行うことで、どの段階でボトルネックが発生しているのかを明確にすることができるでしょう。
また、社内の関係者とのヒアリングを行い、採用活動に対する意見や感想を集めることも効果的です。
関連記事: 採用代行(RPO)とは?料金・費用相場、おすすめ10選を紹介!
企業のよくある採用課題一覧

ここからは、企業のよくある採用課題を一覧にしてまとめて紹介します。
応募が集まらない
採用活動において、応募が集まらないという課題は多くの企業が直面する問題です。特に優秀な人材を確保するためには、まずは応募者数を増やすことが欠かせません。
応募が集まらない原因は様々ですが、主に採用したい人材に適していない採用手法や情報発信の不足、競合他社との違いが明確でないことが挙げられます。
求める人材から応募が来ない
応募者が集まっていても、求める人材から応募が来ていないというケースもあり得るでしょう。求める人材が集まらない状況が長期的に続くと、単純に採用率が低下するだけでなく、選考等による、人事のリソース面での負担も増加するため、早急に対策を講じる必要があります。
よくある理由としては、求める人材像が明確になっておらず、応募者がどのようなニーズを持っているべきか理解できていないまま採用活動を続けていることが挙げられるでしょう。
選考辞退率が高い
選考辞退率が高いという課題は、多くの企業が直面する問題の1つです。選考辞退が多発すると、再度母集団の形成が必要になる場合もあり、採用活動の効率が低下します。
また、辞退した求職者が競合他社に採用された場合、人材面での競争力の低下にも繋がります。
選考過程で候補者が辞退する理由はさまざまですが、選考フローが長いことなど、企業の魅力以外の点が原因の場合もあるため、多角的に原因を分析することが重要です。
選考通過率が低い
選考通過率が低いと採用活動が長引き、コストがかかってしまうだけでなく、結果的に企業の成長に悪影響を及ぼす可能性があります。また、原因が社内のコミュニケーション不足によるものだった場合、本来活躍できるはずの人材を不採用にしてしまうことなどもあります。
原因としては選考基準が不明確であり、人事と役員との間で採用基準にズレが生じていることや、採用要件が厳しかったりすることが挙げられるでしょう。
人材の定着率が低い
企業にとって、人材の定着率が低いことは大きな課題です。定着率が低いと採用活動にかけたコストが無駄になり、業務の継続性にも影響を及ぼします。
特に優秀な人材が短期間で離職してしまうと、チームの士気や生産性にも悪影響を与えるため、早急な対策が求められるでしょう。
人事部門の人手不足
採用活動が活発化する時期には、必要な人材を確保するためのリソースが不足し、業務が滞ることもあります。このような状況では、採用活動の質が低下し、結果として優秀な人材を逃してしまうリスクが高まってしまうでしょう。
優秀な人材からの応募が多くても、人事部門が人手不足では、求職者とのコミュニケーションの質が低下し、結果として、選考辞退が増加してしまう可能性もあります。
応募が集まらない採用課題の解決策

ここからは、応募が集まらない採用課題の解決策について紹介します。
採用手法の見直す
応募が集まらない場合、企業は新たな採用手法を検討する必要があります。まずは、現在の採用手法を分析し、どの部分が機能していないのかを特定しましょう。
求人広告の掲載先だけでなく、内容や選考プロセスなど、さまざまな要素が応募者不足に影響を与えています。そのため、現在行っている採用手法を改善すれば良いのか、新しい採用手法に切り替える必要があるのかという点を慎重に検討することが重要です。
情報発信を強化する
採用活動において、情報発信の強化は非常に重要です。情報発信を強化すれば、企業の魅力や文化、求める人物像を明確に伝え、応募者の関心を引きつけることができます。
特に現代においてSNSや自社のウェブサイトを活用した情報発信は、幅広い層にアプローチができる有効的な方法と言えるでしょう。
発信方法や手法は様々ですが、社員インタビューや職場の様子を紹介する動画を制作し、応募者にリアルなイメージを持ってもらう動画を活用した情報発信は、大企業をはじめ中小企業にも人気のある方法です。
競合他社との差別化を図る
応募者が集まらないときは、競合他社との差別化を図りましょう。多くの企業が同じような人材を求めている中では、自社の魅力を明確に伝えることができないと、優秀な人材を獲得することは難しくなります。
自社の強みや独自性を明確にし、それを基にした採用戦略を構築することが求められるでしょう。具体的には企業文化や働き方、福利厚生など他社にはない特徴をアピールすることが効果的です。
求める人材から応募が来ない採用課題の解決策

ここからは、求める人材から応募が来ない採用課題の解決策について紹介します。
採用ペルソナの設計を見直す
採用ペルソナとは、企業が求める理想的な人材像を具体的に描いたものです。このペルソナを明確にすることで、ターゲットとなる候補者に対して効果的なアプローチが可能になります。
採用活動がうまくいかない場合、ペルソナの設計が適切ではない可能性があるので、採用ペルソナの見直しが重要になるでしょう。現在のペルソナが実際の業務や企業文化に合致しているか確認し、採用データや社員のフィードバックを基に再評価を実施してみてください。
ダイレクトリクルーティングを導入する
ダイレクトリクルーティングは、企業が求める人材に直接アプローチする採用手法であり、近年多くの企業で注目されています。
求める人材からの募集を待つのではなく、企業から採用しに行く「攻めの採用」を取り入れることで、スムーズに採用活動を進めることができるでしょう。
ただし、ダイレクトリクルーティングを行う際には、候補者とのコミュニケーションを大切にし、関係構築を図ることから始めるようにしてください。
選考辞退率が高い採用課題の解決策

ここからは、選考辞退率が高い採用課題の解決策について紹介します。
選考回数を減らす
選考回数を減らすことは、選考辞退率を低下させるための有効な手段です。選考回数が多いと求職者の採用率が下がることはもちろん、人事担当者の負担も大きくなってしまいます。
選考回数が多いことに対して、求職者が抵抗を感じてしまうこともあるので、選考プロセスを簡素化し、必要最低限の回数に抑えることが重要です。
カジュアル面談を活用する
カジュアル面談とは、企業と候補者がリラックスした雰囲気の中で行う面談のことを指します。従来の面接形式とは異なり堅苦しさがなく、自然体での対話が可能なため、求職者が本音を話しやすくなります。
このような面談の機会を提供することで、求職者が企業の文化や雰囲気をより深く理解することができ、選考辞退率の低下につながる効果が期待できるでしょう。
面接の連絡を早める
選考辞退率が高いという課題に対処するためには、面接の連絡を迅速に行うことが非常に重要です。候補者は、複数の企業に応募していることが多く、選考プロセスが長引くと他の企業に先を越されてしまう可能性があります。
そのため、面接の連絡を早めて候補者の自社に対する入社意欲を維持し、選考辞退を防ぐようにしましょう。応募者が書類選考を通過した際に、できるだけ早く面接の日程を提案することが効果的です。
選考通過率が低い採用課題の解決策
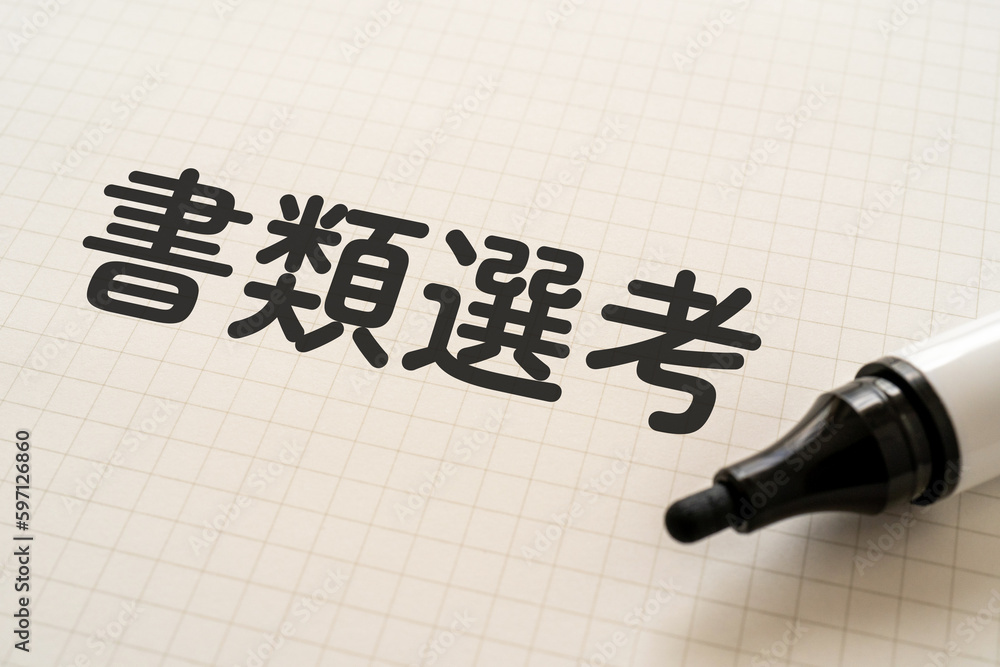
ここからは、選考通過率が低い採用課題の解決策について紹介します。
選考基準を明確にする
選考基準を明確にすることは、採用プロセスの効率化と質の向上に直結します。企業が求める人材像を定義することで、選考における判断基準が一貫性を持ち、候補者に対しても公平な評価が可能です。
具体的な人物像が定まったら選考基準を文書化し、面接官全員に共有することで、評価のばらつきを減少させ、認識の齟齬による不採用を防止することができるでしょう。
採用要件を緩和する
採用通過率が低い場合、企業は採用要件を見直すことが重要です。特に求めるスキルや経験が厳しすぎる場合、優秀な候補者を逃してしまう可能性があるでしょう。
例えば、特定の資格や経験年数を必須とすることで、実際にはその条件を満たさないが、ポテンシャルの高い人材を排除してしまうことがあります。採用要件を緩和しすぎることは危険ですが、厳しすぎてもいけません。
人材の定着率が低い採用課題の解決策

ここからは、人材の定着率が低い採用課題の解決策について紹介します。
求人の情報量を増やす
求人情報の充実は、求める人材を引き寄せるための重要な要素です。多くの求職者は応募を検討する際に求人情報を確認するので、企業は求人票に必要な情報をしっかりと盛り込むことが求められます。
仕事内容や求めるスキルや勤務条件、給与、福利厚生などの基本情報はもちろん、企業の文化や職場環境についても触れることで、求職者に対してより具体的なイメージを提供できるでしょう。
求職者が求人情報を通して企業をよく理解した状態で入社することで、結果として、入社後のギャップを減らし、定着率が向上します。
入社後のフォローを充実させる
新入社員が職場にスムーズに適応し、長期的に活躍するためにも入社後のフォローを充実させることも重要です。定着率が低い企業においては、入社後のサポートが不足していることが一因とされています。
新入社員が不安を感じたり、孤立感を抱いたりすることを防ぐためには、しっかりとしたフォロー体制を整えることが求められるでしょう。
例を挙げると、入社後の研修プログラムを充実させたり、相談を兼ねた簡単な面談を導入したりなどのフォロー体制を整えておくことが大切です。
人事部門の人手不足に対する解決策

人事部門が人手不足の場合は、アウトソーシングを活用することが選択肢の1つとして挙げられるでしょう。特定の業務を外部に委託することで、内部の人員が重要な業務に集中できる環境を整えることができます。
ただし、アウトソーシングを活用するときは費用対効果を考慮することが大切です。アウトソーシングの費用に見合う人材採用を実現できるのか、内部の人員数を調整して対応できないのかなどを考慮し、外部に依頼するか決定しましょう。
まとめ
採用課題は、企業の成長や競争力に直結する重要な要素です。採用活動がうまくいかない理由を理解し、適切な対策を講じることで、より良い人材を確保することが可能になります。
この記事では、採用課題の重要性や具体的な課題一覧、そしてそれぞれの課題に対する解決策を詳しく解説しました。企業が直面する採用課題は多岐にわたりますが、まずは自社の現状を正確に把握することが第一歩です。
現状を分析し、課題に対して適切な対処法を取れば、課題をスムーズに解決することができるでしょう。
参考:障害者雇用の【離職率】は高い?離職を防ぎ長く働く4つの対策 | 障害者雇用Lab
参考:採用課題を解決する採用案内パンフレット|PAMPHLET.make[パンフレット.メイク]
参考:合同会社バオウェン|全ての人が平等に挑戦できる社会へというミッションを掲げ、社会課題の解決を目指す

株式会社キャンパスサポート
ピタリク運営事務局

